自己肯定感とは、「自分をそのまま受け入れる力」ともいえる感覚のことであり、幸福な人生を送る上で欠かせない要素です。自己肯定感が高い人ほど幸福度や生活満足度が高く、仕事や学業、人間関係でも成功を収めやすいと言われています。
自己肯定感が高いことは「生まれつきの才能」ではなく、自分自身を知ることで自己肯定感を上げることができるのです。
本記事では、自己肯定感の基本的な概念とその重要性、さらに具体的な実践方法について解説するので、ぜひご覧ください。
自己肯定感とは

「自己肯定感」とは、上述の通り「自分の弱さも含めて、自分をまるごと受け入れる感覚」です。
他者との比較や評価に左右されることなく、どんな自分でも価値があると思える感覚です。とはいえ自己肯定感については様々な定義があるので、ここではいくつかを紹介します。
田中弘道
本研究では、自己肯定感の定義を「事故に対して肯定的で、好ましく思うような態度や感情とする」。
参考:田中道弘(2005). 自己肯定感尺度の作成と項目の検討 人間科学論究
高垣忠一郎(臨床心理士)
「自分が自分であって大丈夫」という安心感を欠く世界のように筆者には感じられ、その「自分が自分であって大丈夫」という感覚のことを筆者は「自己肯定感」と呼んできたのである。
参考:私の心理臨床実践と「自己肯定感」
文部科学省
自己肯定感については、これまでも様々な捉え方が示されてきましたが、その一つとして、勉強やスポーツ等を通じて他者と競い合うなど、自らの力の向上に向けて努力することで得られる達成感や他者からの評価等を通じて育まれる自己肯定感と、自らのアイデンティティに目を向け、自分の長所のみならず短所を含めた自分らしさや個性を冷静に受け止めることで身に付けられる自己肯定感の二つの側面から捉えることが考えられます。
参考:資料3-2 自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、
上記に共通して言えることは、やはり「自分の弱さも含めて、自分をまるごと受け入れていること」でしょう。
自己肯定感が高い人と低い人の違い
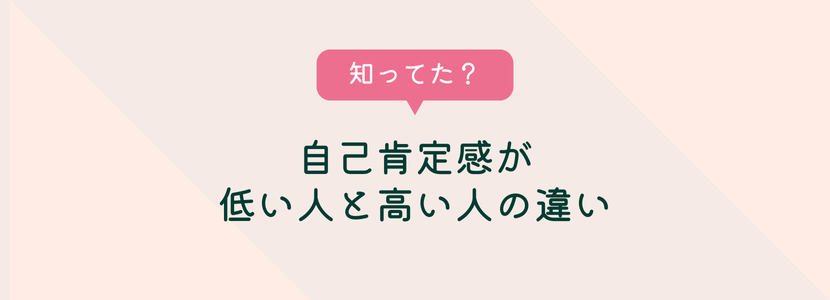
自己肯定感が高い人と低い人には以下のような違いがあります。
自己肯定感が高い人
- 自分の長所と短所どちらも「これが自分だ」と認めている
- 失敗を「成長のためのプロセス」として前向きに考える
- 自分も他者も尊重できる
- 他人と自分を比較せず、「自分には自分のペースがある」と考える
自己肯定感が低い人
- 自分のスキルやスキルは好きになれるが、ダメな自分を好きになれない
- 自分の欠点ばかりに目が向き、「自分は価値がない」と思いやすい
- 他者の評価に依存し「人に認められなければ意味がない」と感る
- 他者の成功や長所を見ると、「自分は劣っている」と比較して落ち込む
- 相手に嫌われることを過剰に恐れ、人間関係に不安を抱きやすい
自己肯定感が低下するのはなぜ?

自己肯定感が低くなることには、以下のような原因があります。
SNSの影響
1日のSNS使用時間が3時間を超える若者は、自己肯定感が平均で32%低下する傾向があると言われています。SNS上で見る他者の「完璧な生活」との比較が、現実の自分への否定的な評価に繋がるからです。
他人の「成功」「楽しそうな日常」「美しい写真」など、表面的に見える「完璧な瞬間」が次々と流れてくることで、自分の現実と比較して劣等感を抱きやすくなります。また、「いいね」やフォロワー数といった数値に左右されることで、自己評価が外部の反応に依存しやすくなるのも自己肯定感の低下に影響しています。
失敗への過剰な恐れ
現代は「結果が全て」という風潮が根付いており、過程や努力が評価されにくい状況があります。失敗が許されない風潮は、自分の行動や挑戦を萎縮させ、失敗を恐れるあまり自己評価が低くなる原因となります。
教育環境の課題
幼少期の教育環境やが自己肯定感に大きな影響を与えることがわかっています。例えば、成績やテストの点数といった画一的な基準で評価されると、「自分の価値は数字で決まる」という認識を植え付ける可能性があります。
「もっと頑張りなさい」「他の子はこれくらいできるのに」といった言葉は、子どもの自己肯定感を下げる要因になります。要するに、子供は条件付きの愛情と見なし、「自分は〇〇ができないと愛されない」という認識を持ってしまうのです。
トラウマや過去の経験
幼少期のいじめや否定的な経験、失敗や挫折の経験が長期的に自己肯定感に影響を与えることがあります。「自分は価値のない存在だ」という思い込みが形成され、自己肯定感が低下してしまうのです。
自分のことを理解していない
そもそもSNSの情報や他人の評価に流されてしまうのは、自分だけの軸が見つけられていないだけの可能性があります。「自分はこういう人間だ」と言えるようになると、他人からの評価が気になりにくくなります。「自己肯定感が低い人≒自分のことを理解していない人」ともいえるでしょう。
自己肯定感を高める実践的方法
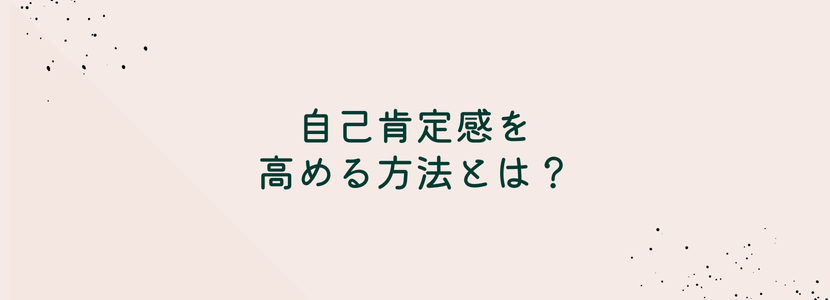
まずは自己理解をする
自分にできないことばかりにフォーカスしてしまう方は、自己理解が足りていない可能性があります。弱みばかりにフォーカスしてしまう方は、「努力が足りないだけだ」と自分自身を責めてしまっているかもしれません。
しかし、自分自身について深く理解することで、「これが自分だ」と胸を張って思えるようになるのです。案外、自分のことは自分が一番理解できていないため、一度ご自身に向き合うことが重要です。
強み・弱みを理解する
自分自身の強み・弱みを根拠のある診断結果を元に知ることで、弱みを克服するのではなく、「そもそも弱みが発揮されない生き方」を考えられるようになります。ご自身の強みを知ったうえで、弱みの対処法もセットで見つけることで、人生をより良く生きられるようになるでしょう。
自分の価値観を理解する
自分は人生で何を大切にしているか?を知ることが大切です。「死」だけは平等に訪れることを前提に考えると、人の評価を気にしている場合ではなくなります。限られた人生の中で、どんな生き方をしたいのか、自分だけの幸せは何かを見つけることで、SNSなどの情報に踊らされない強固な自分が見つかるでしょう。
毎日「良かった出来事」を書き留める
よくある手法ですが、これは幸福度を高めると言われています。手順は以下の通りです。
- 良かった出来事を3つ書く
- なぜそれが起こったのかを考える
良かった出来事だけを書くのではなく、なぜその出来事が起こったのかを書くことで、幸福度が上がります。例は以下の通りです。
良かった出来事:美味しいご飯を食べられたこと
理由:家に帰ったら好物の唐揚げを家族が作ってくれていたから
このように、「なぜその出来事が起こったのか」まで思い出すと、人に感謝できたり、繋がりを感じられたりと、幸福度が上がる要因になります。
自己肯定感は上がるのか?実際に良かったことを書き出してみた!
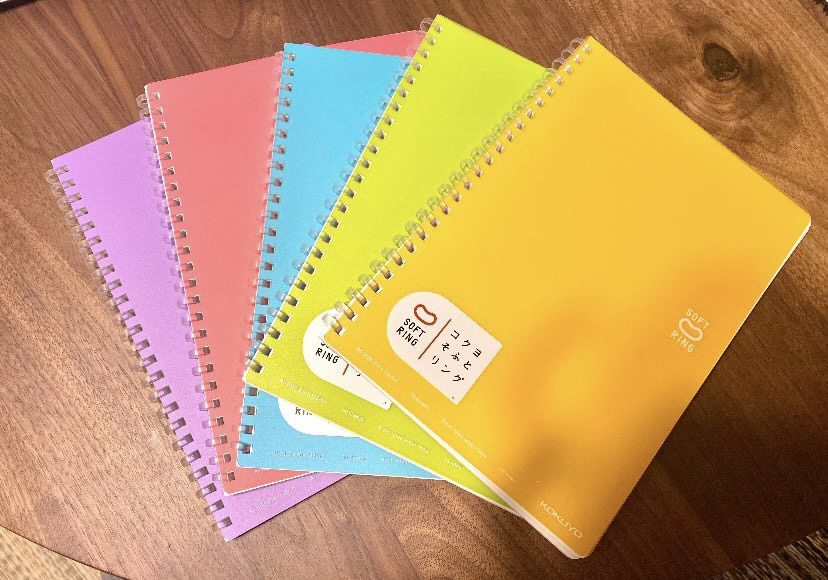
めちゃくちゃ飽き性な私ですが、実際に「良かった出来事を書き留める作業」を10日間くらい続けてみました。
正直なところ、初めは半信半疑で行っていました。しかし、いつの間にか「自分の幸せは誰かのおかげで成り立っているのかも……」と感じられるように。
一例を以下に挙げてみます。
よかったこと:友達と美味しいご飯を食べられたこと
理由:高校の頃から仲良くしてくれていて、今でも関係性が続いているから
こうしてみると、友達との関係性が成り立っているからこそ、自分の人生は豊かなんだ。そして、その友達がいるからこそ、幸せを感じられるんだなぁ……と、感謝の気持ちに変わっていることに気が付きます。
この行動を続けることで幸福感が上がるだけでなく、「自分にはたくさんの人が付いているんだ」という自信になり、自己肯定感の向上に繋がりました。
まとめ
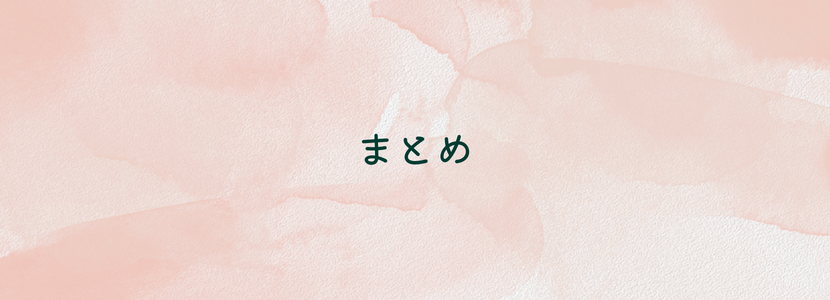
自己肯定感は、私たちの人生の質を大きく左右する重要な要素です。完璧を目指すのではなく、ありのままの自分を受け入れながら、少しずつ成長していく姿勢が大切です。
自己肯定感は生まれつきの性格特性ではなく、適切な理解と実践によって育てることができます。日々の小さな積み重ねが、より健康的で充実した人生につながっていくのです。
ただし、深刻な自己否定感や持続的な心の不調を感じる場合は、専門家への相談をお勧めします。適切なサポートを受けることで、より効果的な改善が期待できます。
合同会社結では、「自分らしさが道しるべになる」という想いのもと、様々な情報発信を行っています。下記の公式LINEに登録した方限定で、「自分軸シート」をプレゼントしていますので、興味のある方はぜひ登録してみてくださいね!

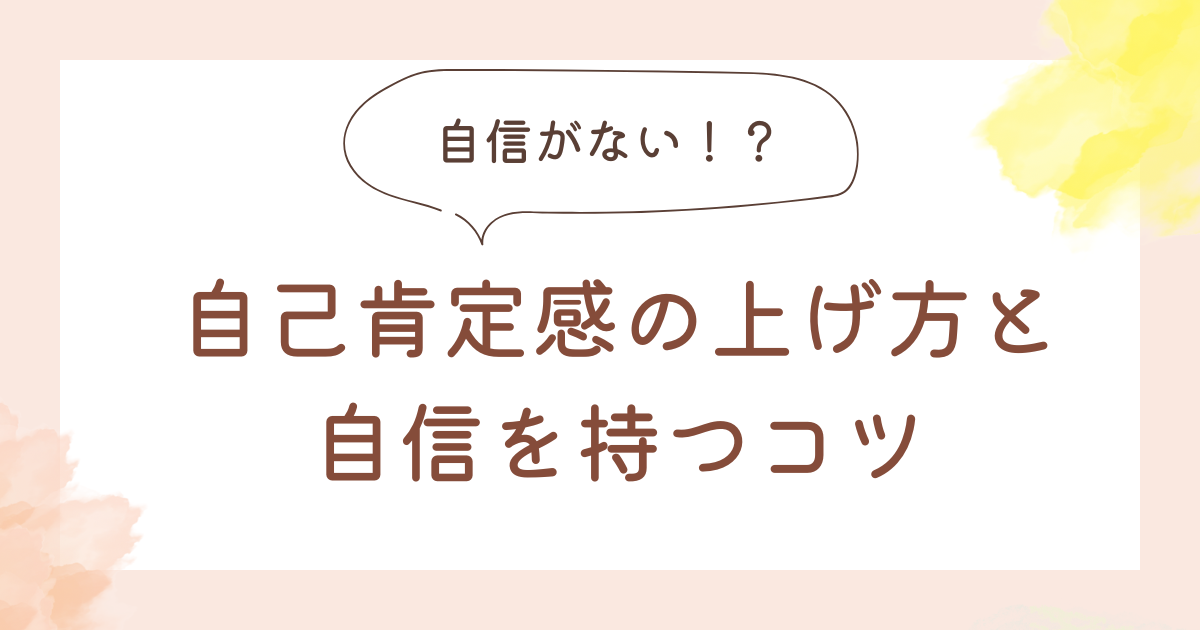
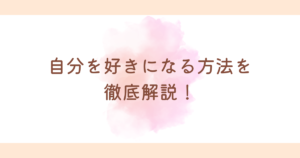
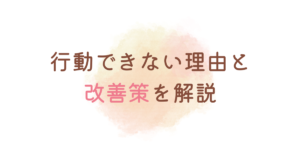
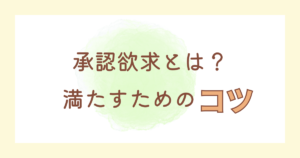
コメント